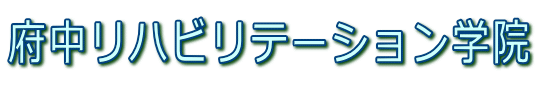東京都立府中リハビリテーション学院・専門学校の沿革
●1968年 7月
開設準備協議会ならびに準備室設置。委員には大島良雄(東京大学教授)、小池文英(整肢療護園長)、芳賀敏彦(東京病院附属リハビリテーション学院学院長補佐)、楢林博太郎(順天堂大学教授)、安原克(東京都衛生局公衆衛生部長)が就任。カリキュラムについては東京病院附属リハビリテーション学院(1963年開設)、建物については九州リハビリテーション大学校(1966年開設)から多くの教示を受けた。
●1968年 9月
●1968年12月
●1969年 1月
●1969年 2月
●1969年 3月
学院本館・車庫着工
学院長に整肢療護園副園長五味重春氏内定
厚生大臣あて理学療法士・作業療法士養成施設の指定申請書提出
第1回入学試験実施。志願者PT156人、OT90人、最終合格者PTOT各20人
学院本館・車庫竣工。理学療法士・作業療法士養成施設として厚生大臣の指定
●1969年 4月
●1969年 5月
●1969年 7月
東京都立府中リハビリテーション学院開校、第1回入学式挙行(機能訓練室)
寄宿舎建設計画に関する学生との話し合い開始
学生自治会発足

●1969年11月
作業棟・講堂・学生寄宿舎着工
(1969年4月 第1回入学式)
●1970年4月
●1970年6月
●1970年7月
●1971年6月
●1972年2月
●1972年3月
●1972年4月
●1973年3月
●1973年10月
●1977年3月
●1977年3月
●1977年12月
●1978年4月
●1979年10月
●1982年4月
●1982年5月
●1985年2月
●1985年4月
●1985年5月
●1986年5月
●1987年3月
●1988年3月
第2期生入学
作業棟・講堂・学生寄宿舎竣工----夏休み明けから入寮。学生により「櫟寮」と命名される。
第1回学生祭の開催
初めてのインターン(長期臨床実習)開始
寮の食費値上げの反対運動の激化・長期化
第1期生(PT16人、OT11人)卒業。卒業生の熱望により、学院長、畑井、楠川、本田各講師による卒業記念講演が行なわれた。
第4期生入学。指定規則改定に伴うカリキュラム改正。
第2期生(PT13人、OT1人)卒業。
同窓会の発足。
学生自治会、大量留年、卒業繰り延べを契機に「学生処分及び成績判定制度に関する要請」を提出
初代学院長 五味重春先生、筑波大学教授へ転出
専修学校制度の改正に伴い東京都立府中リハビリテーション専門学校と改称
二代目校長として神沼誠一先生が就任
創立10周年記念式典挙行
三代目校長 福田敬三先生就任
東京都衛生局に東京都立医療技術短期大学開設準備委員会が設置される。
最後の入学試験
最後の入学式
最後のキャンプ
最後の学生祭
檪寮の閉寮
最後の卒業式。第17期生(PT20人、OT20人)卒業。東京都立医療技術短期大学への移行とともに閉校
東京都立府中リハビリテーション学院(府中リハと略)の思い出
五味 重春 平成14年(2002年)11月16日
1.開校以前
昭和43年(1968年)、整肢療護園副園長として昭和30年以来肢体不自由児の療育に専念している頃、東大整形外科の先輩である故山本浩先生から都立府中リハ設立に協力するよう依頼があった。整肢療護園は、恩師故高木憲次先生の創立によるもので、故小池文英先生が2代目の園長として、昭和38年より活躍しておられ5年が経過し、200床の運営も軌道に乗った所であった。故小池園長に府中リハの事をお話したところ、PT・OTの教育養成は将来固有専門職に委ねるべきで、当分の間担当したらと奨められた。東京都より衛生局永井技監が三顧の礼をもって招聴に見えたので、お引き受けことになった。
昭和43年12月学士会館に於いて設立準備委員会が開催、衛生局公衆衛生部故安原部長、主催委員に故砂原東京病院長、楢林順天堂医科大学教授、芳賀敏彦東京病院付属リハ学院副院長等がおられた。すべては校長予定者一任ということで形式的に委員会は終了。府中病院敷地にリハ学院の建築が進められており、厚生省に開校申請手続き中であった。校長予定者以外の専任教員が無く、申請許可に手間取っていた。先輩校の清瀬の東京病院にならい、専任教員公募を外国PT・OT誌に掲載していた。故砂原院長が二世OT教員候補(Miss M. TERADA)を紹介して下さった。その他の予定者とPT教員は、校長が代行で申請手続きを進められて行った。

(2004年10月 五味先生を囲む会にて)
昭和44年4月、東京都衛生局主幹(身障医療担当)府中リハ学院長事務取扱いとの辞令を頂いた。学生募集、入学試験選抜は厚生省申請中という条件で、衛生局の応援を得て進められた。具体的に開校時準備事務は山口学院次長、高橋庶務課長、根本教務課長、益子教務、坂井教務、瀬川司書、原島庶務、島崎氏らで進められて行った。
2.開校時
入学式は昭和44年4月珍しく春雪の日に府中新校舎で開催された。入学式後に厚生省医療関係者審議会PT・OT部会委員(故岩原寅猪、伊藤久次先生)による実地審査が行われたのが異例であった。
3.開校後の課題
教職員に対するリハビリテーシヨンの理念を如何に徹底させるという大きな命題があり機会教育に努めた。専任教員の外国よりの応募対応も、忙しい課題であった。
昭和44年7月、公衆衛生部(故安原部長)から医務部(松井部長)へ移動した。松井部長の指導で東京都のPT.OT対策を検討する機会を得て、故美濃部都知事へ助言を提出した。この中に府中リハの高等教育化(短大、保健大学)の検討がうたわれている。
4.医療関係者高等教育への道
看護教育と並行して都立保健大学構想の実現準備が進められ、多摩八王子地域の実地調査が行われた。ところが該当地域に文化遺産が発見され、その処理に歳月を要した。
昭和47年、厚生省医療関係者審議会PT・OT部会長故砂原茂一氏らは、PT・OTの高等教育への進展を具申、カリキュラムを添えて厚生・文部大臣宛意見を提出した。昭和47年、東京都は教員候補者の海外留学制度を創設し、府中リハ学院より山口素子さんを第一回生として米国へ派遣した。引き続き鈴木OT、菊池OT、山田OT、高橋PT、森永PT、江原PT、伊藤PTらを米国大学院へ送った。
昭和51年、参議院議員柏原やすさんが府中リハ学院に来訪された。その後、柏原議員は参議院予算委員会で文部・厚生大臣にPT・OT問題に就き質問されている。その答弁は高等教育展開への起爆剤となっていると思われる。
昭和52年、日本学術会議の政府に対するPT・OT等の教育に関する意見具申があり、高等教育化への大きな更なる力となっている。これを機運に金沢大学に三年制医療技術短期学が高等教育機関として創設された。次いで弘前大学等に、順次、短期大学部が増設されてきた。
東京都は、昭和57年、短期大学開設準備委員会を設け、衛生局長崎医務部長らの努力で、昭和61年、都立医療技術短期大学が荒川区旭電化跡地に開設された。新宿看護高等学院、府中リハ学院、放射線技師学校の統合であった。
平成4年4月、広島大学に医学部保健学科PT・OT専攻の4年制教育創設。東京都長期計画の一環として短期大学の4年制大学昇格準備が進められ、鈴木都知事(金平副知事担当)は、平成12年度計画を2年前倒しで平成10年度開学に踏み切った。平成14年には大学院(修士課程)をも荒川の地に開校された。
府中リハ学院から33年にして大学院までの道は、多くの人々の力の結晶であり、都民のリハビリ医療の基礎となることを信じ、将来への進展を期待している。
府中の地を訪ね「ここにリハビリテーシヨンの学び舎ありき」を観て頂きたい。
※本書簡は、平成14年(2002年)11月にホテルオークラで行われた「五味先生を囲む会」の際に、五味先生から寄せられたものです。
(1期PT卒 倉石氏より提供)