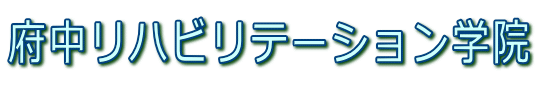同窓会の歩み
・・・1988年発行の同窓会誌(閉校記念)より抜粋
■巻頭言 同窓会活動
(閉校記念同窓会誌<1988年>より抜粋)
池田 誠 (1988年当時の同窓会長)
1969年4月開校した東京都立府中リハビリテーション学院(後に専門学校)は、19年間(17期)続いて1988年3月閉校となった。我々卒業生は、この学校を通じていろいろな意味で人生のなかに様々な思い出を創り出してきたと思う。校舎は、閉校となった今も(8月1日)、櫟寮とともにまだ解体されずひっそりと建っている。いずれ壊されて「記念碑」のみになってしまうであろう。そのとき我々は、改めて廃校という「状態」が理解できるだろう。しかし、目にみえなくなったのは校舎・櫟寮のみでともに学んだ教職員、632人の学友はまだまだ健在であるはずである。その意味において、同窓会の存在をいままで以上にもっと明確にしなくてはならないと考える。廃校後、発展的な意味で開学した東京都立医療技術短期大学とどのような方法で関係を創り上げていくのか、我々としてまだ十分な議論をできる状態ではない。廃校となった他専門学校(新宿看護・診療放射線)と同じように同窓会の活動については短大の中の一部屋の共同利用が認められているのみである。いずれにしても短大の学生が卒業してから考えていく問題であろう。
このような現状で我々同窓会がいま考えておかねばならないことは、同窓会員の集まりの「場」を確保しておくことと、少しでも会員同士のコミュニケーションをはかっておくことなどであろう。その意味において「セミナー」の継続が求められよう。そして会員同士の情報交換が出来る同窓会の運営形態をもっと模索する必要があるだろう。
東京都立府中リハビリテーション専門学校同窓会は、卒業生集団が理学療法・作業療法の世界のなかで、また異なった世界のなかでしっかりと羽ばたいている「姿」をこれからも見守り続けて行きたいと考えている。
■同窓会の歩み
(閉校記念同窓会誌<1988年>より抜粋)
倉石 健二 (第1期卒 PT)
学院の同窓会の歩みをお話しする前に、学院の歴史からお話しを進めてゆきたいと思います。昭和40年代に入り東京都は日本国の首都として巨大代が進み、種々の障害が出てきました。その中で市民運動がさかんになり都政も保守派だけでは都民の要求に対して十分な対応が出来なくなりました。この流れの中で美濃部さんがあのスマイルで、また学者として、シビルミニマム構想をひっさげて都政に登場してきました。美濃部知事は御存知のように革新系であり多くの市民団体の支援を受け当選し、この美濃部都政のシビルミニマム路線に乗って浮上してきたのが我母校であります。昭和44年(1969年)4月開学となりました。天下の代々木ゼミから入学して来た小生にとってあまりに小さな校舎をみて、ただ唖然とするばかりでした。そして昭和47年3月めでたく3年間で卒業いたしました。卒業と同時に同窓会が設立されたのではなく、第2回生が卒業の時に会が設立されました(昭和48年でしょう)。同窓会が出来たのは何となく卒業生の団体があってもよいのでは程度の考え方が大勢であり、同窓会は学校運営に当り在校生が不利益をこうむらないような圧力団体となるべきである等と考える人は殆んどありませんでした。
同窓会が出来たものの活動は皆無であり、同窓会費すら卒業時に頂くだけで毎年の会費などはありませんでした。この様な情況の中で自然消滅してゆくのを待つばかりの会でありましたが、昭和52年に一回生の有志が集い、第一回五味記念府中セミナーが学院講堂で開かれました。2年後第3回生を中心として第2回府中セミナーが開かれました。(五味記念のネーミングは確か御本人が非常に嫌がられたのではずしたと記憶しております)この主催を同窓会でするという意見が出されました。これが会の実質的活動を行なった初めてのケースです。この案を考え出された諸兄は本当に頭脳明析な諸士であろうと考えております。ちなみに小生はこの案に大反対でした。時は流れ府中リハ学の卒業生の中にもお勉強が好きな人が多くなり府中セミナーも毎年のように開かれ同窓会総会とカップルで行なわれるようになり、また同窓会役員の大変な御苦労で会員名簿を作って頂いた時もありました。この様にして今日に至っています。現在本学がその使命を終わり廃校という時期に同窓会のゆく道を皆さんと共に考えてゆきたいと思う今日この頃です。
もう一つ大事なことがあります。同窓会には"弘美基金"と云う基金があります。これは昭和52年に学院の江原皓吉先生のお嬢ちゃんが天に召されたおり先生より同窓会に役立ててほしいという御希望により浄財を寄附して頂いたものです。当時の役員でこのお金の利用方法について集り"弘美基金"として同窓会に貢献した者、学術的に秀れた業績を残した者に何か記念品を送る基金として利用させて頂くことに決定して現在に至っております。(基金の名称はお嬢ちゃんのお名前をつけました。)
■閉校にあたって
(閉校記念同窓会誌<1988年>より抜粋)
高橋 正明 (第3期卒 PT)
私の学んだ小学校も中学校もすでにこの世にない。過去を振り返ることが好きでない性格なのか、あるいはまだ若かったせいか、それを寂しいと感じたことはなかった。私にとってまた一つ学舎が消える,,今年度で府中リハビリテーション専門学校がその歴史を閉じるのである。今回は寂しさと同時に不安にさえも襲われる。安息の場だけでなく自分の足場さえ消えて行くような不安である。
昭和53年だったと思うが、学校に残っているという理由だけで佐藤章先生から同窓会の会長職を引き継いだ。そして昭和56年度に学校を辞めるにつき北目茂先生に引き継いでもらった。同窓会長を引き受けて最初に手をつけた懸案事項は、いかにして同窓会費を集めるかであった。当時は年会費制であった。旧会則は年会費の滞納者を除名することができた。ところが実際には年会費を納める会員は皆無だったのである.
同窓会の執行部に年会費を徴収するだけの人的、時間的余裕はないこと、年会費未納に対する除名処分は同窓会の本来的性格に馴染まないことが反省として出され、会則の大幅な改正に至った。会則の改正にあたり役員会ではそれなりの議論はあった。一方は、卒業生が必然的に会員になるのだから会費納入義務を設けるのはおかしい。他方は、卒業生以外でも学校に在籍あるいは在職すれば会員となる権利があるのだから、義務として会費を納めるのは当然である。ところが実際は、年会費の徴収能力のない執行部が、いかにして年間活動費を捻出するかというのが本音の部分だったような気がする。結局、取れるところから取れということになり、卒業目前の学生から、入会費を終身会費として徴収することになった。会計をされていた山川邦子先生から、卒業したら同窓会に入るのは当然で、入会する以上入会金を納めるのは当り前という顔をすれば、100%徴収可能であるという心強い発言もいただき、何とも乱暴かつおおらかな決定がなされたのである。
新会則における会員の義務を唯一、氏名、住所、身上の移動を事務局まで報告することとした。そこに同窓会の基本的な存在理由があると考えたからである。同窓会とは同窓のよしみを制度的につないでおこうとする組織であり、何かの折りに、ふっと心和ませるきっかけを提供する会なのであろう。どうでも良いようなものながら、その実、個人のidentityとしっかり結び付いていて、学舎が無くなり、年を追えば追うほど、その役割が一層貴重となるように思う。同窓のよしみが発展して社会的に影響力を持てば喝采したくなるし、そうでなくても一会員であることを誇り高く思い続けられる会なのである。
ただ、今にして残念なのは、弘美基金を運用するだけの力が我々には無かったことである。同窓のよしみが存在する以上、今後にその可能性を期待するのも悪くは無いと思っている。
これまでの同窓会活動
■府中セミナー
1979年(昭和52年)、第1期生有志が集い、親睦だけでなく学術交流を図ることを目的として、第1回五味記念府中セミナーを開催。第2回セミナーは、2年後の1981年(昭和54年)、第3期生が中心となって開催され、以後、同窓会総会と合わせて定期的に開催された。閉校後も1992年までは継続されたが、1993年からは移行した東京都立医療技術短大の卒業生と合同で「T-Fセミナー」として開催され、1996年まで継続された。
■同窓会誌および名簿の発行
1988年の閉校を記念して、翌19889年に同窓会誌(名簿付)が刊行された。それから6年後の1994年に更新された同窓会名簿が発行・配布されたが、異動の把握が次第に難しくなってきた。現在は、個人情報保護の観点から名簿発行は行われていない。
■弘美基金による会員の研究支援
1988年(昭和63年)の同窓会総会で弘美基金の活用方法が検討され、会員の研究費として1件10万円×4件の資金援助を募集することとなった。そして、1988年に応募のあった2件、1991年に応募のあった2件の研究に対して、それぞれ10万円ずつ資金援助が行われ、利子による残額は同窓会予算の繰越金とともに管理されてきた。
■閉校記念碑の建立
1988年の閉校にあたり、閉校記念碑を建立すべく関係各位の協力の下、同窓生から寄付を募り、1989年11月18日、校舎跡地に閉校記念碑を建立、除幕式が行われた。碑文は初代学院長五味重春先生による「ここにリハビリテーションの学び舎ありき、共にこの道を拓かん」。
■同窓会活動の休止
1994年に同窓会名簿を更新発行してから以降、実質的な活動は停滞してきたことから、1997年の総会において、閉校10年を節目として、一旦、同窓会活動を休止し、次の方向性を模索することとなった。
■五味先生の慶事に合わせた祝賀事業の開催
-
1978年(S53年) 最初の五味先生を囲む会
-
1989年(H元年) 3月 1期生による「五味先生を囲む会」(静岡裾野市のペンション「南の風」にて)
-
1993年(H 5年) 7月 東北在住の卒業生と下北旅行(喜寿のお祝いを兼ねて)
-
1994年(H 6年) 6月 五味先生の叙勲を祝う会
-
2004年(H16年) 10月 米寿の祝い 五味先生を囲む会
-
2006年(H18年) 10月 卆寿祝いとして計画⇒同窓生交流会へ変更 参加者97人
新たな同窓会活動として
府中リハ同窓生交流会の開催
・・・2014年より2年ごとの開催を目標に
■府中リハ同窓生交流会2014開催趣旨・企画
(開催案内より抜粋)
都立府中リハ学院・専門学校同窓生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
府中リハ開設期の1・2期生は退職の時期を迎え、閉校期の16・17期生は20年選手としてご活躍のことと思います。
平成18年に全体での同窓会を開催して以来、8年が経過しました。都立のPTOT養成校としては都立医療技術短大を経て、現在の首都大学東京健康福祉学部へと継承されていますが、同窓会としては「府中リハ」としての絆が強いせいか、現在の形で今日に至っております。それもやはり、青春時代の3年間過ごしたあの武蔵台での共通の思い出がそうさせているのではないかと思います。
そこで、今回、8年ぶりに、思い出の武蔵台ウォーキング・ツアーを含めた同窓生交流会を、下記の要領で企画いたしました。10月は各種学会・セミナー・研修会の季節でもあり、ご多用のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
(2014年9月吉日)
発起人代表
對馬 均(府中リハPT2期卒業)
佐藤 章(府中リハOT2期卒業)
記
●開催日 2014年10月25日(土)
●第1部 15:00~16:30(自由参加)
思い出の武蔵台ウォーキング・ツアー
●第2部 19:00~21:00
同窓生交流パーティ
・会 場: パレスホテル立川
・会 費: 8,000円
■当日の様子は同窓生交流会のページをご覧ください
■同窓生交流会2014終了報告
2014年10月25日に開催されました「府中リハ同窓生交流会2014」にご参集いただいた皆様、いかがでしたでしょうか。同期の仲間だけでなく、先輩、後輩との懐かしい語らいを通して、私たちのルーツを改めて再確認することができたように思われます。最後に撮った集合写真と交流会の収支決済報告書については、同窓生交流会のページをご覧ください。
今回の交流会の案内を広く行なうために、試験的にホームページを開設しましたが、旧同窓会会長である高橋正明氏と相談の結果、このホームページを今後の同窓生の拠点として稼動させることとなりました。ここに至るまでには、次のような経緯がありました。
1977年に発足した「東京都立府中リハビリテーション専門学校同窓会」は、1988年の閉校以来、活動の拠点を失った形となり、その存続のため、さまざまな努力が払われて来ました。しかし、年を経るごとに発足当初の趣旨と会則に沿った形で同窓会を組織的に維持することが困難となり、8年前に開催された同窓生交流会(当初は五味先生の卆寿祝賀という企画だったが、五味先生体調不良により交流会に変更)の席上、いったん組織を解消し、実情に合った形での存続を模索することが提案され、了承されていました。
そこで、今回の交流会を好機として、ホームページを同窓会の拠点として位置づけ、試行的に運用し、情報発信・交換の場とすることとなった次第です。
ホームページを開設するに当たり、同窓会専用のドメインとレンタル・サーバーを契約しましたが、この年間費用は、旧同窓会からの繰越金から賄われました。今後、この繰越金を財源として継続的にホームページを運用していくことをご承知おき下さい。
2014年11月1日
同窓生交流会発起人代表
ホームページ管理者
對馬 均(府中リハOT2期卒業)
今後の活動目標
■Webサイトを通した同窓生の情報交換
■2年に1度のペースで同窓生交流会の開催